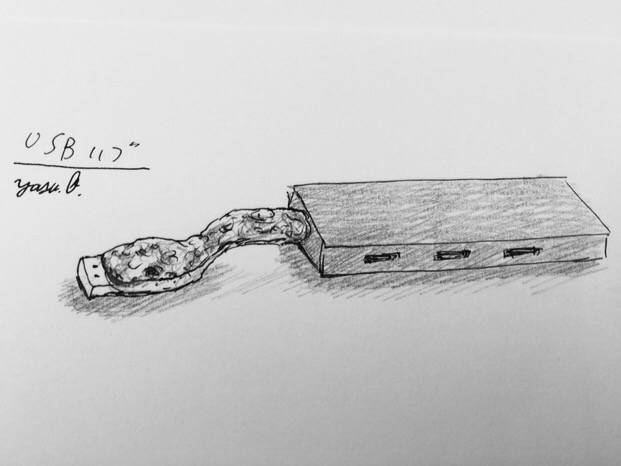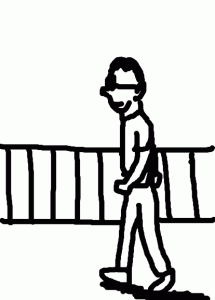このところ大いに盛り上がっているように思える、AI(人工知能)。そのAIのプログラミングにPhython(パイソン)というプログラミング言語が向いているようだ。PhythonでないとAIのプログラミングができないわけではないものの、AIのプログラミングに適した言語のひとつであるらしい。
株式会社UEIの代表取締役・清水亮さんはPhythonについてブログでそのように書いていたし、同社が開催しているAIプログラミング教室(講座というべきか)でもPhthonなどによる深層学習プログラミングに取り組んでいるようだ。
ところでこのPhython、私はその存在を知っていたという程度で、Phythonについて特に詳しいわけではないが、その名称は前々から気にならないではなかった。パイソン。そう、英国のあのコメディ集団をご存知の方も少なくないだろう。
モンティ・パイソン
私はモンティ・パイソンの活躍をタイムリーに、つまり同時代的に感じながら少年期を過ごしたわけではないが、大学時代以降くらいにモンティ・パイソンにふれるようになった。
以前、下北沢に住んでいた頃に「ドラマ」という名のレンタルビデオ店で何本も借りて見始めたように思う。見始めることになったのには、劇作家・演出家の宮沢章夫さんによる影響があるのは間違いないだろう。
1990年代前半から後半にかけて、私は宮沢章夫さんが主宰する「遊園地再生事業団」の公演に何度も足を運び、池袋西武のコミュニティカレッジで開催されていた宮沢さんによる演劇のワークショップにも通っていたことがある。
そのワークショップで宮沢さんは、モンティ・パイソンの映像を流したりしていて、変な歩き方をするコントの「シリーウォーク」(という回といっていいのだろうか、妙な歩き方を大真面目な表情でする男たちが登場する)などを目にした。いま、コントと書いたが、モンティ・パイソンのなかでは「スケッチ」という表現が使われていたはずだ。
このPhythonという言葉はもともと「ニシキヘビ」という意味の英語で、Wikipediaには「Phyhonは、オランダ人のグイド・ヴァンロッサムが開発した。名前の由来は、イギリスのテレビ局BBCが製作したコメディ番組『空飛ぶモンティ・パイソン』と記述されている(2017年10月2日現在)。