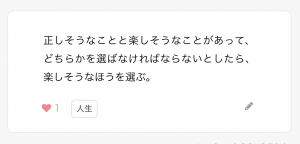リクルートの住宅情報誌『都心に住む』で連載されていたショーとストーリーをまとめた書籍『坂の記憶』。これは、クリエイティブ・エージェンシー「TAGBOAT」の岡康道さんと麻生哲朗さんが順番に書いていたもので、同誌は月刊誌であるから、それぞれの打席は2カ月に1度巡ってきたという計算になる。と野球にたとえる必然性はないが、ストーリーの中に野球が何度か登場する。
野球好きで、自らのオフィスの屋号を「ベースボール」としている私は、特にグッと来たのかもしれないが、さまざまなの坂のそば暮らす人の人生の起伏や、小さなドラマが詰まった短編小説集である。
波乱万丈の人生を活写したような大きな物語というより、どこにもでいそうな人物の、どこにでもありそうでその実、どこにでもはないかもしれない小さな物語の、人生の一瞬(人生のある短期間)を切り取ったようなストーリーの数々。まさに、スライス・オブ・ライフといっていい、小気味のいい切り取り方だろうか。
大成功というわけではなく、大失敗というわけでもなく、ささやかな幸福が感じられるような物語が32。それぞれ、400字詰め原稿用紙に換算して、6枚弱程度のボリュームだろう。深夜のテレビ番組とテレビ番組の間の5分から10分くらいを使って、ドラマとして放送してくれたらぜひ観てみたいと思えるような、そんな小品。
32の坂と(1つの坂を除いてすべて東京の坂)、その数倍の人間が登場し、それぞれの物語を生きている。岡さん、麻生さんの、人間を見つめる眼差しがやさしい、僕にはそう感じられる。いわゆる、成功者というのはほとんど出てこない、というのもいいのだろう。著者の二人は、日本の広告業界では知らぬ者がいないといえるほどの成功者といってもいいが、本書における、エリートでないものを優しく見つめるような眼差しが心地よい。
すべての書籍にいえるわけではないだろうが、僕が以前から感じていた「ビジネス書は成功者やエリートを描き、小説は失敗した者や非エリートを描く」という範囲にも当てはまる(当てはまることが悪いというつもりまったくはなく、だからこそ受け入れられるのだろうという意味で、私は肯定的に見ている)。
このショートストーリー群に触発されたのか、いくつもの橋が存在する下町に暮している私は、橋の物語を紡いでみようかな、そんな気がしてくる。
『坂の記憶』
著者:岡康道さん、麻生哲朗さん
発行:SPACE SHOWER BOOKS
カテゴリー
- 560s
- advertisement
- app
- art
- audible
- baseball
- book
- business
- comic
- dream
- flower
- food
- football
- game
- gif
- good
- goods
- haiku
- html5
- idea
- illustration
- investment
- JavaScript
- kaibun
- kindle unlimited
- linestamp
- movie
- music
- noncategory
- novel
- okulabcolumn
- okulabworks
- ookr
- pet
- photo
- plant
- poem
- poet
- programming
- radio
- sketch
- sports
- thinking
- tokyoskytree
- tutorial
- web
- WordPress
- work
- writing